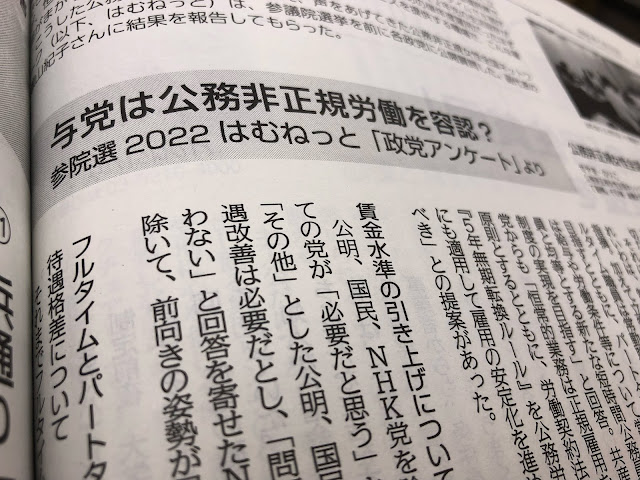戦争「当事者」の「記憶」を忘れないために

今年の2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻。その教訓を、4つのキーワードを元に考えたい。4つとは、「リアルタイム」「普遍的規範」「当事者」そして「記憶」だ。 圧倒的多数の世界の人々が心を痛めているのは、戦争の状況をリアルタイムで見ているからだ。テレビとインターネットを通じて、今、起こりつつあるウクライナ市民の悲しみ、苦しみが目に入る。子どもや女性、老人たちが殺され、住居、学校、病院等が破壊され、数百万もの人々が避難民として国外に逃げる有様を目の当たりにしている。 他方、リアルタイムの報道がされなかったために、私たちが「知らなかった」戦争があることも記憶しておこう。 人類普遍の規範とは この戦争を非難し、悲劇を終らせなくてはという思いの基準になっているのは、人類普遍の規範だ。「国際法違反」「非人道的」「民間人」という言葉を挙げるだけでその意味は十分伝わるだろう。 しかし、歴史を振り返ると、全世界がそのような基準で判断しなかったケースも多くある。例えば、1945年3月10日の東京大空襲では、一晩に10万人もの民間人が亡くなった。さらに、8月6日と9日の広島・長崎への原爆投下が多くの民間人の命を奪い、長期間にわたる悲劇の元になったことは言うまでもない。しかし、当時その行為を、世界が「国際法違反」だとか「非人道的」だと非難することはなかった。他方、アメリカやアジアで「当然の報い」という声が大きかったことは良く知られている。 ここでは、民間人の犠牲に焦点を合わせているので、国家の加害責任についてはまた別の機会に論じたい。 傍観者と当事者 ウクライナで起きていることの「教訓」として、日本も攻められないように「核共有」や「核武装」をすべし、あるいは改憲によって軍事力保持を正当化すべし、そして軍事費を倍増して強い国にすべきだという主張が、戦争好きの人たちから発信されている。その主張を鵜呑みにする前に、これが「傍観者」である人々の主張であることに注目しよう。 「当事者」であるウクライナのゼレンスキー大統領は、日本の国会に向けた演説の中で、核保有や軍事力の強化が必要だなどとは言っていない。彼のメッセージは「このような戦争を予防できる国際機関を、日本が中心になって運営して欲しい」なのだ。 わが国でも、民間人として、また当事者として生き地獄を体験した被爆者や戦